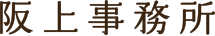インボイス制度導入後も売上税額の計算は割戻し計算が原則となりますが、自社が交付した
インボイスに記載された税額を積み上げて計算することも認められます。
仕入税額の計算は、受け取ったインボイスに記載された消費税額を積み上げて計算する「請求
書等積上げ計算」原則となります。ほかに帳簿積上げ計算、割戻し計算も採用できますが、一部併用で
きないケースがあるので注意が必要です。
顧客等への対応
インボイスの発行について、取引先から問い合わせを受けることが想定されますので、
インボイス制度を理解し、問い合わせがあった際の対応方法を確認しておく必要があります。経理部門だけでな
く営業担当・営業事務等にもインボイス制度を周知し対応方法を共有しておきましょう。
- POSTED at 2023年01月16日 (月)